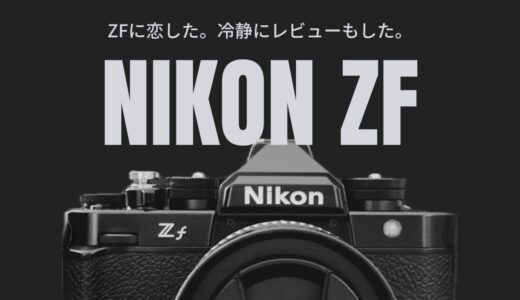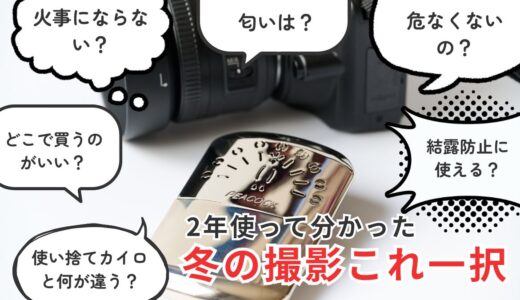当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
- レンズは “カビる” って聞くけど、それってヤバいの?
- レンズにカビ生えたらもう使えない?
- 防湿庫って本当に必要なの?
カメラやレンズにカビが生えるなんて、自分には関係ない…そう思っていませんか?
でも、レンズのカビは “誰にでも起こりうる” 身近なトラブルなんです!
そもそも、日本の環境はカビにとっての「パラダイス」だと、ご存知でしょうか。
カビが生えると、写りが劣化するだけでなく、レンズなどの資産価値まで大きく損ないます。
だからこそ、カビに対する正しい知識と予防が必要となるのです。
この記事では、有効なカビ対策や、湿度の管理方法などを分かりやすく解説しています。
僕自身、カビ予防に力を入れるようになってから、一度もカビに悩まされていません!
実体験をもとに、大切なレンズを守るための方法をお伝えしますね。
- はじめてレンズを購入した初心者の方
- 防湿庫の購入を迷っている人
- 将来、レンズを売るときに「損」をしたくな人
【忙しいあなたへ】結論として、おすすめの商品はこちらになります!
∟【Yahoo!ショッピング】トーリハン ドライキャビ PD-55
カメラやレンズのカビは、 “誰にでも起こる” 身近なトラブル

実は、僕も最初は「まさか自分のレンズに…」と思ってました。
でもレンズに潜む “静かな破壊者” は、すでに動き出しているかもしれません。
カビ対策ってやった方がいいの?
カメラやレンズを扱う上で、「カビ対策」は最優先で取り組むべきことだと感じています。
特にレンズはカビが発生しやすい、 “デリケートな道具” なので注意したいところですね。
ぶっちゃけ、レンズが増えてから対策するのではなく、最初の1本から対策すべきなのです!
このように言い切れる理由が、主に次の2つとなっています。
- カビが生えると…解像度が落ちてしまう。
- カビが生えると…レンズの資産価値が下がってしまう。
近年暑さが増していて、「昔こんなに暑かったっけ?」と感じている人も多いのではないでしょうか。
実際、日本の夏は世界的に見てもかなり過酷で、「湿度」がそれに拍車をかけています。
暑い国といえばアフリカなどが思い浮かびますが、気温が高くても湿度はかなり低めです。
一方、日本の夏は30℃を超える猛暑に加え、湿度も80%以上になる日が続きますよね。
だから、体感温度は日本の方が高い!なんて言われる中で僕らは生活しています。笑

この「高温多湿」の環境こそが、カビの繁殖にとって理想的な条件なのです。
こうした日本の環境において、 “レンズはカビやすいもの” という認識を持つことが大切です。
なので日本に住んでいる限り、カビ対策からは逃れられないとも言えますね。
「レンズがカビるなんて大変」と他人事に感じるかもしれません。
ですが、 “明日は我が身” です。
最初は、点のような小さなカビも、放置するとレンズ表面に膜のように大きく広がります。
まるで、クモが巣を張ったような見た目になりますよ!
こうなると「ピントは合ってるのに、なぜかボヤける」という解像度の低下に繋がります。
(よく言えば、オールドレンズ風の柔らかい写り、とも言えなくもないかもしれませんが…。)
でも、狙ってないのにボヤけるってやっぱり致命的ですよね。
そこからカビがレンズ内部まで侵食してしまうと、被害はどんどん拡大します。
中でも怖いのが、レンズのカビがカメラ本体にまで移ることです。
レンズに近接しているイメージセンサーに、カビが繁殖してしまうことがあるんです。
こうなると修理に出すしかなく、最悪の場合は買い替えるしかないなんてケースも…。

「今使ってるレンズは大丈夫?」と不安になった人は、実際にチェックしてみましょう!
やり方はとても簡単で、
- 照明などの光源にレンズの前玉をかざす。
- 裏玉側からのぞいてみる。
(※強い光を見るので、目を痛めないように注意してくださいね。)
白いモヤのようなものが見えたらカビの可能性が高いです。
そして、カビ被害において僕が1番痛いと感じるのが、「資産価値が下がる」ことです。
そもそもレンズって、 “資産価値が落ちにくい道具” ですよね。
ところが、一度カビが生えてしまうと、その価値は大きく下がってしまうんです。
買取時に「カビあり」と判断されれば、当然価格は大幅ダウンとなります…。
このようにレンズを資産としても大切にするなら、カビ対策は絶対に避けて通れません。
とはいえ、「どうやってカビ対策すればいいの?」と不安に思う方も多いと思います。
そこで次では、カビに対する予防策などを分かりやすく紹介していきますね。
プロに任せないと危険? レンズのカビ取りで起こる最悪の結末

「カビが生えても拭けばOKでしょ」なんて油断していませんか?
その油断が、取り返しのつかない一歩かもしれません。
カビなら取り除けるよね?
カビが生えてから対策するのでは、修理不能となるケースがあることを強調したいです。
つまり、「予防」こそが最強のカビ対策であると思います。
とはいえ、レンズにカビが少しでも生えていたら手遅れ…ということでもありません。
ひと口に “カビ被害” と言っても、重度・軽度があるので、それぞれに分けて解説しますね。
まず、軽度のカビ被害であれば、ワンチャン自分自身で対処することも可能です。
「軽度」というのは、レンズ表面にうっすら付着した程度のカビを指します。
具体的なやり方は…
- ブロアーでレンズ表面のホコリなどを吹き飛ばす。
- クリーニング液を使ってカビを優しく拭き取る。
という、2ステップで行うのが基本となります。
自分でカビ取りをするのは手軽な反面、レンズ損傷のリスクがあることも考慮しましょう。
例えば、 “力を入れすぎてレンズのコーティングを痛める” なども考えられますし。
特にオールドレンズなどは非常に繊細なので、慎重に扱う必要があります。
自分でやるのが不安な人は「プロに任せる」ことをおすすめします。
「カメラのキタムラ」では、レンズ表面の薄いカビなら1,000円で除去してくれるようです。
(僕自身は利用経験がないので、ネットで調べた限りの情報ではありますが…。)
予約不要で店頭に持ち込めば、その場で対応してくれるみたいですよ。
ただし、レンズ内部にカビが浸食しているような重度のケースでは、話が変わってきます!

この場合、カメラのキタムラでもメーカー修理扱いになることが多く、費用が高くなります。
内部のレンズ群を交換する必要がある場合、数万円以上の修理費用を覚悟しましょう。
また、古いレンズだと部品が手に入らず、修理不可能として返却されることもあるそうです。
だからこそ「予防」が最強のカビ対策となるわけですね!
こうしたリスクや費用を考えると、やはりベストなのはカビを “生やさない” ことです。
カビ予防なら、お財布はもちろん、精神衛生上も優しいと言えるでしょう。
では、具体的にどうすればカビの発生を予防できるのでしょう?
以下の3つのステップを意識してみてください。
【効果的なカビ予防① 】汚れを落として清潔に保つ

カビは皮脂や手垢、ホコリなどをエサにして繁殖します。
なので、撮影後はそのまま放置せず、軽く汚れを拭き取る習慣をつけたいですね。
そして、レンズ表面を掃除するなら「レンズペン」を使うのがおすすめです。
手軽でムラも出にくく、日常のメンテナンスにぴったりです。
やはり、面倒くさくないのが良いですよね!
でないと、汚れをこすってしまいレンズに傷が入る恐れがあります…。
【効果的なカビ予防②】とにかく使ってやることが大切

意外かもしれませんが、レンズは使っている方がカビが生えにくいものです。
例えば、ズームレンズなら使うことで、内部の空気を循環させることができます。
可動部が動くことで、内部の空気が滞らず、カビが繁殖しにくい環境になるのです。
「もったいないから使わない」ではなく、定期的に使うことでメンテナンスにもなるんです。
人間と同じで動かないとダメになるってことですね。
【効果的なカビ予防③】保管環境を整えることが超重要

どんなにメンテしても、保管環境が悪ければ、ぶっちゃけ意味がありません。
日本のような高温多湿の環境では、適切な湿度管理がカビ対策の要になりますし。
「防湿庫」は1番確実で手間いらずの対策法ですよ!
そんな防湿庫ですが、多くの人が最初に使うのは「乾燥剤」を入れるタイプだと思います。
以前、僕も使っていたので分かるのですが、乾燥剤式は何かとデメリットが多いんですよね…。
一方、電気で動く「ペルチェ式」の防湿庫であればノーストレスでカビ対策ができます。
高温多湿な日本において、特にペルチェ式防湿庫は「必須アイテム」だと断言できます。
次では、 “ペルチェ式防湿庫の何が良いのか” を深掘りしていきます。
湿度70%、「ちょ…カビるって!」防湿庫で守るカメラの命

いきなりですけど、湿度って目に見えないですよね?
だから、お金を出してまで防湿庫が必要なのか迷う気持ち、痛いほど分かります。
本当に防湿庫を使う必要ある?
もしあなたが、レンズの資産価値を守りたいなら、防湿庫は100%使うべきです!
レンズは中古でも価値が残りやすいので、資産価値が高いものとして知られています。
だからこそ、カビで台無しにしてしまう前に “予防” することが大切です。
カビが繁殖しやすい日本では、必要かどうかより「使わないとヤバい」とすら感じてます。
カビが最も活発になるのは、気温20~30℃、湿度60%以上の環境となります。
特に湿度がクセ者で、70%を超えたくらいから、空気中のカビ胞子が発芽するんです。
このときレンズ表面などに胞子が付着すると、カビが繁殖してしまうのです。
この条件とは、まさに日本の梅雨や夏そのものですよね!
つまり、日本に住んでる以上、 “放っておけばカビが生えて当たり前” ということなんです。

ではなぜ「防湿庫の購入を迷うのか」ですが、湿度が目に見えるものじゃないためでしょう。
防湿庫は湿度を管理する道具なので、 “目で見て分かる変化がない” ことは明白なのです。
買った直後ですら、「効果があるのかな?」と疑いたくなる気持ちがありますし…。笑
でもその“目に見えない脅威”が、レンズの寿命を静かに縮めているかもしれないのです。
また、レンズにとって理想的な湿度は「40~50%」となっています。
ただし、湿度が40%を下回ると、レンズに使われるゴム素材が硬化するリスクもあります。
つまり、ただ除湿すればいいというわけではないんです。
40~50%という狭いレンジを、安定して保つ必要があるんですね。
この狭いレンジでの湿度管理こそ、防湿庫が得意とするところなのです!
そんな防湿庫ですが、主に2つのタイプがあります。
先ほども少し触れましたが、「乾燥剤式」と「ペルチェ式」です。
まず、多くの人がとりあえず使ってみるであろう「乾燥剤式」を見てみましょう。
これらのメリットは次の3つにあると感じます。
- 初期費用の安さ。
- 電源が不要で設置場所を選ばない。
- 小型だから初心者のハードルが低い。
でも僕自身が使って感じたことなのですが、思ったよりもデメリットが多いんですよね…。

まず、1番大きなデメリットとして、「湿度調整の難しさ」があげられます。
乾燥剤の量で湿度をコントロールする必要があるのですが、これが至難の業なのです。
乾燥剤を放り込むだけでは、湿度が下がりすぎることもしばしば…。
となると、防湿庫の蓋を開けるなど工夫が必要になるんですが、現実的じゃないですよね。
そしてこの乾燥剤の交換が、思いのほか面倒なんです。
“半年もつ” はずの商品でも、3ヶ月くらいで交換時期になることもありますし。
(北海道など湿度の低い地域なら、また変わるのかもしれませんが…。)
乾燥剤は安いんですけど、買い置きを忘れると管理できなくなります。
頭の片隅に乾燥剤のことを考えないといけないのがしんどいんですよね。
また、安価な防湿庫は「収納不足になりやすい」とも感じました。
カメラにハマると、どうしても手持ちのレンズは増えていきますよね。
そのうち入らなくなって、より大きな防湿庫が欲しくなるのは目に見てます。
となると、最初から大きい防湿庫を買っておく方が、ムダがありませんよね。

そこでおすすめしたいのが、ペルチェ式の防湿庫です。
ちなみに僕は、「トーリ・ハン」というメーカーの防湿庫を愛用しています。
ペルチェ式の防湿庫になりますが、あまりの使いやすさに感動しました。笑
そこで、乾燥剤式のものと比べて「良いな」と思ったポイントをいくつか紹介していきます。
まず、湿度が1%単位で調整できることがあげられます。
これによって、レンズが理想とする湿度40~50%のキープが容易となります。
最初に湿度を設定さえすれば、あとはフルオートで管理してくれるので、手間もありません。

また、トーリ・ハンのドライキャビは、25L~220Lといった豊富なラインナップも魅力です。
僕のは50Lですが、大きな望遠ズームレンズでも、縦・横気にせず使えます。
デザインも洗練されているので、インテリアとしても機能すると思います。
除湿ユニットはペルチェ式となっていて、5~10年は持続して使うことができます。
もし壊れても、「除湿ユニットを交換できる」のも心強いですね。
また、ペルチェ式は高い除湿力だけでなく、 “ほぼ無音” な点も気に入っています。
僕は寝室に置いてますけど、夜中でも全く気になりませんよ。

このように、トーリ・ハンの防湿庫は、効率的にレンズの状態をキープしてくれます。
レンズは資産ですし、防湿庫は「安心を変える道具」だと感じています。
面倒なことは機械任せで、あとは毎日の撮影を楽しむだけです。
安心して長くカメラを使いたい人にこそ、防湿庫は必須のアイテムなのです!
∟【Yahoo!ショッピング】トーリハン ドライキャビ PD-55
【まとめ】カビは待ってくれない。だから今こそ防湿庫を

カメラやレンズにとって、日本の高温多湿な環境は「まさにカビの温床」と言えます。
一度カビが生えると、写りの劣化はもちろん、資産価値すらも下がってしまいます。
だからこそ、カビが生えてからではなく、「カビを生やさないための対策」が大切なのです!
日常のメンテナンスに加えて、最も確実でストレスのない対策が「防湿庫」の導入です。
湿度を1%単位でコントロールできるペルチェ式の防湿庫は、まさに “レンズの避暑地” ですね!
湿度を理想の環境でキープしてくれるので、管理の手間もなく、撮影に集中できますよ。
僕が愛用している「トーリ・ハン ドライキャビ」については、別記事で詳しく紹介しています。
使用感やサイズ選びの疑問にもお答えしているので、ぜひこちらもチェックしてみて下さい。
レンズの資産価値を守りたい人は、マストで防湿庫を導入しましょう!